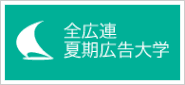第12回
愛広協実践広告ワークショップ 実施報告

※ホームページ制作の都合でPPTファイルで制作された方もPDFファイルに変換しております。
テーマ
「マーケティング&クリエイティブ」
第12回愛広協実践広告ワークショップは、2月8日(土)第1講座に24名、3月8日(土)第2講座に21名の受講生が参加し、開催しました。
今回(株)アラクスの講師から出された課題は、「体外診断用医薬品、チェックワンシリーズの認知を獲得するとともに他社の体外診断用医薬品との差別化を図るコミュニケーション戦略の提案」というもので、難題だったにもかかわらず、独創的なアイディアが多数発表されました。
講座終了後、ただちに審査会を開催し、『AICHI AD AWARDS 2025 学生広告賞』の選定を実施。4月の愛知広告協会定例理事会での承認を得て、グランプリ、準グランプリをはじめとする各賞を決定しました。
実施概要
名称
第12回
愛広協実践広告ワークショップ―「マーケティング&クリエイティブ」
主催
一般社団法人 愛知広告協会
協力
株式会社新東通信、公益社団法人全日本広告連盟
目的
マーケティング&クリエイティブに関心のある、学生を対象にした広告ワークショップ。講座内では実践的な課題を提示しコンペティションを実施する、広告業界の"今"を学ぶ講座の開設。
開催場所
株式会社新東通信名古屋本社
講座日程
第1講座[2月8日(土) 9:50~17:30]
(株)アラクス1名、クリエイター2名の計3名の講師から広告業界の現在の環境をレクチャー、プレゼンテーション課題を発表。
第2講座[3月8日(土) 9:50~16:30]
審査員と受講生を前に一人7分の制限時間内に「制作した広告作品」をプレゼンする。
受講生
公開応募による、愛知県下の専門学校・大学の学生
第1講座:24名
第2講座:21名
講義風景
《第1講座 2月8日(土)》

プレゼン審査風景
《第2講座 3月8日(土)》

課題テーマ
「(体外診断用医薬品)チェックワンシリーズの、認知差別化を図るコミュニケーション戦略の提案」
講師及び審査員プロフィール(敬称略)
《講師及び審査員》
松下 昌弘/ まつした まさひろ
株式会社アラクス
執行役員 企画部 部長
1966年宮城県生まれ。1989年荒川長太郎合名会社(現株式会社アラクス)入社。営業部、研究開発部を経て2004年より企画部、2018年より現職。コミュニケーション領域全般を管轄し、目指すところは専ら企業・ブランド価値の向上。
須田 和博/ すだ かずひろ
株式会社博報堂
UoC/エグゼクティブ・クリエイティブディレクター
1967年新潟県生まれ。1990年博報堂入社。アートディレクター、CMプランナーを経て、2005年よりインタラクティブ領域へ。2009年「ミクシィ年賀状」でTIAAグランプリ。2014年スダラボ発足。第1弾「ライスコード」でアドフェスト・グランプリ、カンヌ・ゴールドなど国内外で70以上の広告賞を受賞。2016~17年 ACC賞インタラクティブ部門・審査委員長。2019年「MRミュージアム」で日本イベント大賞グランプリ。2021年より博報堂UoC所属。2023年より多摩美術大学・非常勤講師、および内閣府SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)ピアレビュー委員。著書「使ってもらえる広告」
𡈽橋 通仁/ どばし みちひと
株式会社 電通中部オフィス
クリエイティブディレクター/アートディレクター
名古屋の山崎デザイン事務所に10年間在籍。2008年電通中部支社入社。近年の仕事は、メニコン/シヤチハタ/中京TV/藤田医科大学/三和交通・TAXI WHISTLE/葵鐘会・Mother Book/マクドナルドハウスを名大病院へ2億円募金CP/他多数。賞歴は、カンヌライオンズ・グランプリ他、国内外で多数。カンヌ審査員等多数歴任。
審査員講評
松下 昌弘
株式会社アラクス
執行役員 企画部 部長
ワークショップに参加された学生の皆さま、この度はご参加いただき、誠にありがとうございました。
今回のテーマである妊娠に関連する検査薬チェックワンシリーズについて考えていただくことは、コンペティションのために用意した架空のものではありません。皆さんが実ユーザー年齢とも隔たりがあるが故に、これまでの経験だけをベースに向き合うのではなく、実際に日本社会で起こっている少子化問題などを整理し、売り場の確認や使用経験者の声を拾うことなどを通じて、検査薬市場が抱える課題を深く掘り下げなければゴールにたどり着けない、極めて難易度の高いテーマでした。しかし、これから広告の世界で仕事に就きたいという志を持つ方々向けのワークショップということで、この課題を設定いたしました。
皆さんは現状を整理し、深い洞察力によって課題の根幹を見つけ出し、売り方、パッケージング、教育などの様々なカテゴリーに由来する斬新なアイデアを掛け合わせてブラッシュアップし、課題の難易度の高さを難なく乗り越えてプレゼンテーションしてくださいました。今回はコンペティションという視点でプレゼンテーションに臨み、各賞を選定しましたが、それとは別に実際にチェックワンシリーズのプロモーション策として展開をしてみたいと思うプレゼンテーションもありました。
皆さんの努力と情熱の1か月が、私にとっても実のあるワークショップとなったことに改めて心から感謝しています。皆さんがこれからも成長を続けられ、いつの日か広告制作の現場で再開することを期待しています。
最後に、今回のワークショップにお声掛けいただいた愛知広告協会の事務局の皆さま、当日の運営でお世話になった新東通信の皆さま、ありがとうございました。
須田 和博
株式会社博報堂
UoC/エグゼクティブ・クリエイティブディレクター
今回の課題は例年にも増して難しいと思っていました。それは商材がデリケートなものであること、薬事法に関連して広告訴求が制限されること、少子化の加速や未婚非婚者の増加など大きな社会問題を他人ゴトでなく当事者として受けとめて課題に答えなければいけないこと、などなど二重三重に難易度が高いと思っていたからです。ところが、課題発表の当日、驚くべき思考とクオリティで次々とプレゼンが行われ、驚きました。
「ゲームにして理解促進する」「サブスクにして提供する」「抵抗感のないパッケージにする」「トイレに自販機を置く」などなど、どれも等身大のリアリティのある提案で素晴らしかったです。それらを俯瞰した時に気づくのは、課題を自分に引きつけて自分たちだから気づくことができる解決策を提案するのが、結局一番強いという事実です。
今回の課題に限らず、上の世代の人々が下の世代に期待するのは、若いからこそわかる・見つけられる解決策だと思います。上の世代でも考えられる解決策は欲していない。なぜなら自分らで考えられるから。ここに若い世代のチャンスがあるのだと思います。先輩の面子を潰す必要はないのですが、先輩の世代では気づかない着想を提示してあげるのは、とても大事なことだと思います。
今回、質疑応答の時間に「アイデアを考え表現を作る時に、自分の感覚にしたがった方が良いのか?それとも相手にわかってもらうために、相手の感覚に合わせた方が良いのか?そこに迷う」という質問が出たと思います。この質問はあらゆる学生コンペのイベントで良くでる質問です。SNSネイティブ世代だから、よりヒトの価値判断に合わせなければ、と無意識に思うのかもしれません。
しかし、この問いに答えるならば「自分が良いと思ってないもので、相手に合わせに行ったとしても、それを相手が良いと思うはずがない」ということになるでしょう。独善はわかってもらえませんが、ただ合わせに行ってもツマラナイだけ。「わからない」も「ツマラナイ」も共にアイデアとは言えない代物で、「わかる!」かつ「面白い!」こそがアイデアです。それは何度も考えて、何度も形にして、何度も人に見せて、だんだんとわかってくるものなのです。
若い世代だからこそ、わかる・気づけるアイデアを、上の世代や広く一般の方々に「なるほど!面白いね!」とわかってもらえるように提示して行くこと。それは広告業界に限らず、どの業界でキャリアを得ていくのにも大事なことだと思います。ご自身の考えを信じて、かつ他者にもわかるように。ひきつづき、がんばってください。
𡈽橋 通仁
株式会社 電通中部オフィス
クリエイティブディレクター/アートディレクター
プレゼンがすべて終わったあと、学生のみなさんに感想を聞くと「緊張した」「うまくできなかった」などの感想はありつつも、毎年きける言葉が「同じ課題にとりくんだけど、色々なアウトプット表現がこんなに出てくるとは思わなかった。それを学べた」というもの。わたしも同感です。私自身今年の課題がハードルが高そうだなと思っていたこともあり。直前になって「もしかしたら、一ヶ月がんばってきてくれた学生のみなさんへのアドバイスがうまくできないかも」と思い自分でもアイデア出ししてから二回目のワークショップに参加しました。しかし私の心配はどこ吹く風でバラエティにとんだユニークなアイデアに驚かされ、インテグレーテッドな考え方をしてくる学生に感心しました。ふりかえれば人材育成に必要なのは ①高いハードル設定 ②時間をかけること だと私自身思っていて、松下さんの課題は人材育成の①にばっちりはまっていたし、全力で一ヶ月という期間をとりくむということは②の条件にもぴったり。プレゼンを終えた参加者全員に成長がみえました。もちろんそこに至るまでの学校の先生たちの教え方が素晴らしいこともあるし、このワークショップを開催してくれるスタッフのみなさんのおかげもあります。せっかく成長を感じ取れたなら、一回目のワークショップで教えた「アイデアの種のつくり方」をぜひ続けてみてください。学びの成長段階には「知る」「わかる」「行う」「できる」「続ける」「教える」「成長する」の7つがあるそうです。今回みんなは「知る」「わかる」「行う」まではいけたと思います。人によっては「できる」まで到達したひともいるもしれない。でもそのつぎの「続ける」が本当に難しいのです。さらにその先にある「教える」はもっと難しくて相手の立場にたってものごとを考えるクリエイターになることが必須。教えることで信念がうまれ矛盾がなくなります。最終的には社会貢献できるようなものが創れるクリエイターになって欲しい。クリエイティブの意味を閉じずに拡げれる人材になることを祈ってます。
※ホームページ制作の都合でPPTファイルで制作された方もPDFファイルに変換しております。